
【森本】 まずは、レクメド・ベンチャーキャピタル設立の理念を、当時の業界や産業の状況を踏まえてお話いただけますか。
【牛田】 1号ファンドを組成したのは、2000年2月のことです。当時は、米国のバイオ産業が大変な活況の中にありました。その背景として、1990年代後半に、IT等の他分野の技術やサイエンスがバイオ研究に積極的に取り入れられ、人間の生命の設計図にあたるゲノムの解読競争が国際的に活発に行われておりました。そして、2000年、米国政府がヒトゲノムの解読が完了したという発表を、当時のクリントン米大統領も同席してホワイトハウスで行いました。これは6カ国による共同プロジェクトだったのですが、世界中で大きなニュースとして取り上げられました。ただ、ゲノムが解読できたといっても、それは、ヒトの生命の設計図が、まだおぼろげに見えてきたという段階にすぎないもので、実際には、その設計図が意味するところを明確にしないと、応用技術の開発への進展はできないのです。
【森本】 しかし、このニュースをきっかけに、バイオベンチャーの株がナスダックで暴騰をし、バイオバブルが発生していったわけですね。
【牛田】 はい。しかし一方で、そのころの日本のバイオ産業は、残念ながら、このゲノムの解読競争に必ずしも貢献できてはいませんでした。ゲノム解読を支えていた企業は、ほとんどが米国企業で占められていて、日本のバイオ産業は、質、量ともに、かなり遅れていたといっていいと思います。そこで、1999年くらいから、これではいけないと、官民を挙げた日本のバイオ産業の育成の動きが活発になります。たとえば、大学などの研究機関で進められるバイオ研究の成果を、起業化、事業化させていくシステムとして、各大学にTLOという技術移転機関を作りました。こうした仕組みができれば、それをしっかり機能させるための資金を供給する体制も必要になってきます。政府の助成金だけでは、当然、限界がありますので、そこで、民間のベンチャーキャピタルの活用が模索されることになりました。
【森本】 証券会社などの金融セクターが中心となり、バイオベンチャーに資金を提供するファンド展開のプランが進められるようになりました。
【牛田】 そこで、本社のレクメドでも、野村證券の発案により創薬分野のバイオに軸足をおいたベンチャーファンドであるLFVF1号(ライフサイエンス投資事業組合)を立ち上げることになったわけです。このファンドは、我々とmblVCという医学生物学研究所を母体にするベンチャーキャピタルとが共同ゼネラルパートナーになって、目利き、ファンドレイズ、ファンド運用を担っています。
【森本】 2000年を過ぎると、日本でもバイオブームが起きます。
【牛田】 ちょうどITバブルがはじけた直後ということもあって、一挙にバイオへの投資熱が高まりました。私たちの1号ファンドも、バイオにまったく関係のない事業会社が出資するという現象がありました。また、これからバイオ分野に投資しようとするベンチャーキャピタルが、我々の投資案件を見てバイオを勉強をする意味で出資する例も多くありました。1号ファンドは、総額34億円となりました。
|
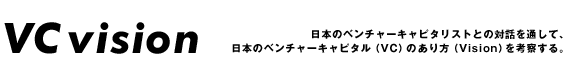






 【森本】 その時期に、他のベンチャーキャピタルでバイオファンドを立ち上げたところはありましたか。
【森本】 その時期に、他のベンチャーキャピタルでバイオファンドを立ち上げたところはありましたか。 【森本】 このバイオファンドの草創期の3社にそれぞれ特徴的な違いはあるのですか。
【森本】 このバイオファンドの草創期の3社にそれぞれ特徴的な違いはあるのですか。