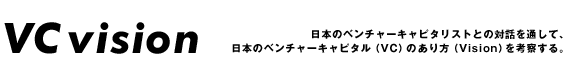 
現在、ITX株式会社は、ライフサイエンス事業、ネットワーク&テクノロジー事業、
モバイル事業、ビジネスイノベーション事業の4つのカテゴリーで事業を展開している。 それぞれのコア事業の事業展開を軸に、 グループ会社各社の人材、ノウハウ、ネットワーク、情報を駆使して、 投資育成できることが同社の強みだ。 interviewer:森本紀行(ベンチャー座アドバイザー、HCアセットマネジメント代表取締役社長) 

インタビューを終えて
|
起業家・ベンチャーキャピタル・投資家を繋ぐコミュニティ・マガジン |
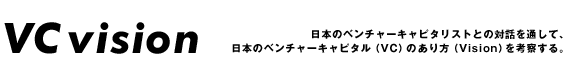 
現在、ITX株式会社は、ライフサイエンス事業、ネットワーク&テクノロジー事業、
モバイル事業、ビジネスイノベーション事業の4つのカテゴリーで事業を展開している。 それぞれのコア事業の事業展開を軸に、 グループ会社各社の人材、ノウハウ、ネットワーク、情報を駆使して、 投資育成できることが同社の強みだ。 interviewer:森本紀行(ベンチャー座アドバイザー、HCアセットマネジメント代表取締役社長) 

インタビューを終えて
|